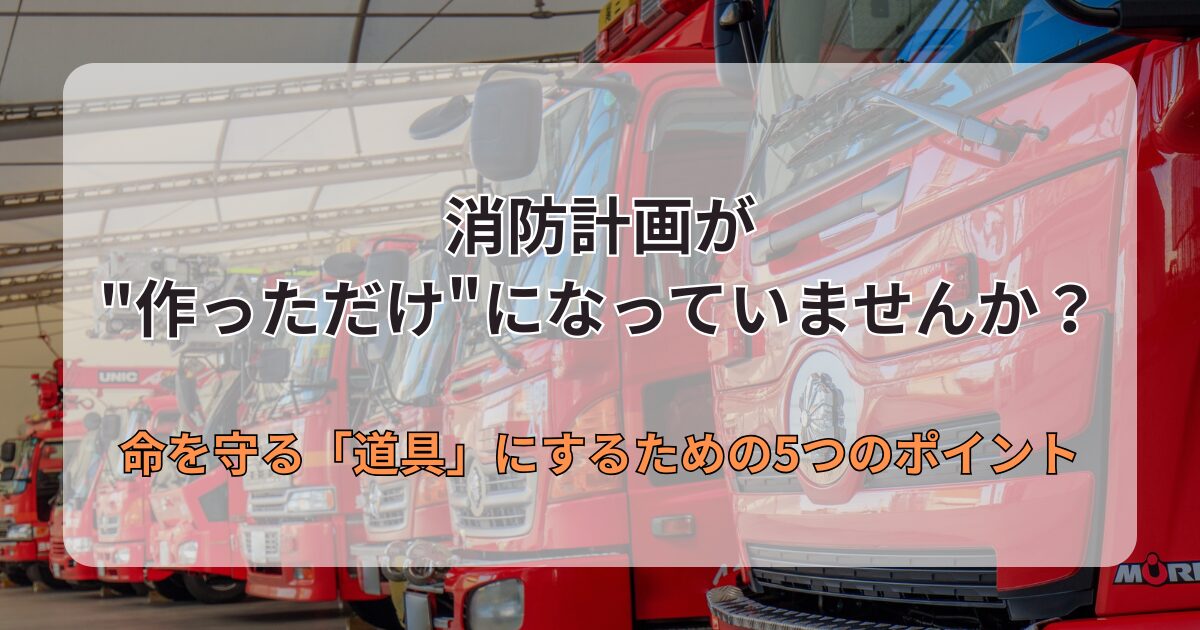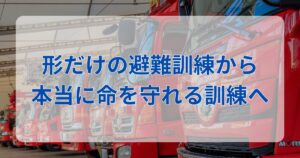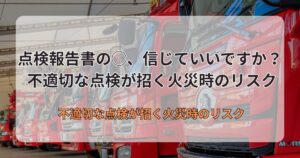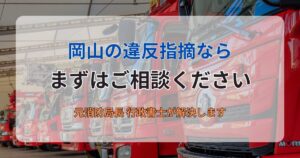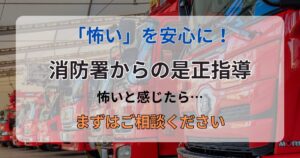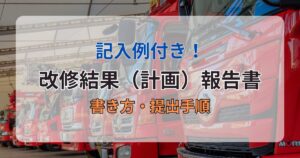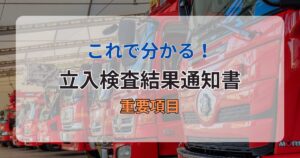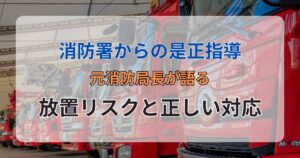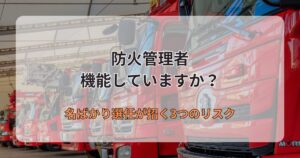「消防計画?ああ、開業時に作って提出しましたよ。確か、棚のどこかにファイルがあるはずです」
経営者の皆様、こんな状況に心当たりはありませんか?

私は岡山市消防局で42年間勤務し、局長として多くの事業所を見てきました。
消防計画が「作っただけ」の状態になっている企業もありました。
2025年8月18日、大阪・道頓堀の雑居ビルで火災が発生し、消防士2名が殉職されました。
このビルは2023年の立入検査で6項目の指摘を受けながら、一部が未改善のままでした。消防計画はあったのです。
しかし、実態は計画通りではありませんでした。
消防計画は「提出するための書類」ではなく、「従業員の命を守る道具」です。
使えない道具を持っていても、いざという時には何の役にも立ちません。
なぜ、消防計画は「作っただけ」になるのか?
総務省消防庁の検討部会でも、消防計画の形骸化が課題として指摘されています。なぜこのような状況が生まれるのでしょうか。
理由1:開業時に「義務だから」作っただけ
多くの事業者様は、開業時や用途変更時に消防署から「消防計画を提出してください」と言われて、初めてその存在を知ります。
- インターネットでテンプレートを探してきた
- 業者に依頼して「とりあえず通る書類」を作ってもらった
- 「受理されればOK」と考えていた
つまり、最初から「使う道具」としてではなく、「通すための書類」として作られているのです。
理由2:誰も見ない、使わない、更新しない
作成後の消防計画は:
- 事務所の棚の奥に眠っている
- 防火管理者が変わっても引き継がれない
- 避難訓練でも計画書を開かない
- 従業員のほとんどが存在すら知らない
東京消防庁の報告書でも、「消防計画の記載内容は形骸化が見受けられた」と指摘されています。「消防署に提出した書類」であって、「災害時に使う道具」ではない。こういった実態の企業も少なくありません。
理由3:現場の実態と乖離している
私が立入検査で確認してきた消防計画の多くは:
- 施設の図面が古く、現在のレイアウトと違う
- 記載されている防火管理者が既に退職している
- 避難経路が、増設した設備で塞がれている
間違った情報に従って行動することで、かえって混乱を招くリスクすらあるのです。
行政も認める「形骸化」という課題
これは個別企業だけの問題ではありません。
総務省消防庁の専門家会合報告書では、以下のような課題が指摘されています:
- 自衛消防組織の消防計画が形骸化している部分がある
- 想定外の大規模震災が発生した際、ソフト面の機能が麻痺する可能性
- 関係者不在施設では、従来の防火管理制度や訓練内容が実態にそぐわない
さらに、防災白書でも「避難訓練内容の形骸化」が課題として挙げられています。



つまり、岡山に限らず、全国的に同じ状況であると言えます。
道頓堀火災が教える「計画があっても守れない」現実
2025年8月18日の道頓堀ビル火災では、出火直後に炎が建物の外側を伝い、約1分で上階へ急拡大しました。
このビルには消防計画がありました。しかし:
- 2023年の立入検査で火災報知器や避難訓練など6項目の指摘
- 一部は未改善のまま
- 避難訓練の指摘もあったが、実施されていなかった可能性
消防士のお二人が殉職されたこの火災は、私たちに重い問いを投げかけています。
「計画があっても、機能しなければ命は守れない」
あなたの消防計画は大丈夫?
5つのチェックポイント以下の質問に、いくつ「はい」と答えられますか?
1. 計画書をすぐに取り出せますか?
消防計画がどこにあるか、すぐに言えますか?防火管理者以外の従業員も知っていますか?
多くの企業では、誰も場所を知りません。
2. 記載内容が現状と一致していますか?
- 防火管理者の氏名は現在の担当者ですか?
- 避難経路図は最新のレイアウトですか?
- 消火器の位置は図面と実際で合っていますか?
総務省消防庁の令和3年データによると、防火管理者の選任が義務付けられている建物は全国に約108万件ありますが、選任されていない建物が相当数存在します。
3. 従業員が内容を理解していますか?
従業員に「火災が起きたら何をする?」と聞いて、答えられますか?
専門用語だらけの計画書を、災害時のパニック状態で読んで理解できる人は、ほとんどいません。
4. 計画に沿った訓練をしていますか?
避難訓練は、消防計画に書かれた手順で実施していますか?
訓練で見つかった問題を、計画に反映していますか?
防災白書では「訓練内容の形骸化」が指摘されています。
多くの企業では、計画と訓練が別々に行われているのです。
5. 定期的に見直していますか?
最後に計画を見直したのはいつですか?
人事異動、レイアウト変更、設備の増設があったとき、計画も更新しましたか?
ほとんどの企業では、開業時のまま一度も更新されていません。
5つ全てに「はい」と答えられた方は、いますでしょうか?
はいと答えられた方は、今の状態を維持して欲しいと思います。
ただ正直、かなり少ないのではないかと思います。
果たしてそれで従業員の命を守れるでしょうか?
現場で本当に使える消防計画に必要な5つの要素
では、「作っただけ」の計画を、「命を守る道具」に変えるには何が必要なのか。
42年間の消防経験から導き出した、実効性のある計画の5つの要素をお伝えします。
【要素1】誰が読んでも理解できる言葉
よくある計画書:
「自衛消防組織の通報連絡班は、119番通報を実施すると同時に、防火管理者及び統括防火管理者に対し火災発生の事実を報告し……」
使える計画書:
【火災を発見したら】
1. 大声で「火事だ!」と叫ぶ
2. 119番通報する(例:「○○ビル3階で火災。逃げ遅れなし」)
3. 店内放送で避難を呼びかける災害時にパニック状態でも行動できる、短く、具体的な表現が必須です。
【要素2】「誰が」「何を」するかが明確
よくある計画書:
「初期消火班は、消火器等を使用して消火活動を行う」
使える計画書:
【初期消火担当】
・主担当:山田太郎(店長)
・副担当:佐藤花子(副店長)
・使用器具:レジ横の消火器(ABC粉末10型)
・消火中止の判断:天井に火が届いたら即座に避難
・不在時:当日の最年長スタッフが担当抽象的な「班」ではなく、実名と具体的な行動を記載します。
【要素3】現場の「今」を反映した図面
避難経路図が実際のレイアウトと一致していなければ、かえって危険です。
チェックすべきポイント:
- 消火器・消火栓の位置が実際と合っているか
- 避難経路上に障害物(棚、設備、備品)がないか
- 増築・改装後の変更が図面に反映されているか
最低でも年1回、現場を見ながら図面を確認する仕組みが必要です。
【要素4】判断基準が数値・状態で示されている
「状況に応じて判断する」では、災害時に判断できません。
具体的な判断基準の例:
- 初期消火の中止:「天井に火が届いたら」「消火開始から2分経っても消えなければ」
- 避難開始:「火災報知器が鳴って3分以内に火元が確認できない場合」
- 119番通報:「消火活動より先に通報」
迷わず判断できる基準を設定します。
【要素5】そのまま使える「セリフ」が書かれている
災害時は冷静に話せません。だから、読めば良いセリフを計画に書いておきます。
119番通報のセリフ:
「火事です。住所は○○市○○町1-2-3、○○ビルの3階です。
○○という会社で火災が発生しています。逃げ遅れはありません。
私の名前は○○、電話番号は090-xxxx-xxxxです」これを電話機の近くに掲示しておけば、誰でも正確に通報できます。



保育園はこのセリフを電話のところに置いてるところは多く見られます。ただ企業となるとほとんど見ることはありません。
計画の見直しで変わった企業の例
見直し前の状況
- 開業時に作成した消防計画が、数年間一度も更新されていなかった
- 記載されている防火管理者が既に退職していた
- 避難経路図には、現在は存在しない機械の配置が描かれていた
- 従業員の多くが、消防計画の存在を知らなかった
- 避難訓練は「形だけ」で、従業員も真剣に取り組んでいなかった
見直し後の変化
実施したこと:
- 現場を隅々まで調査し、最新の図面を作成
- 従業員にヒアリングし、実際の動線を確認
- 役割分担を明確化し、各担当者に個別説明
- A4片面1枚の要約版を作成し、全員に配布
- 計画に基づいた実践的な訓練を実施(予告なし訓練を含む)
その結果:
- 避難完了時間が大幅に短縮された
- 従業員全員が自分の役割を理解した
- 避難経路が明確になり、迷う人がいなくなった
- 「自分たちの命を守る計画」という意識が芽生えた
今すぐできる3つの行動
専門家に依頼する前に、今日からできることがあります。
アクション1:消防計画を探して、開いてみる
まず、消防計画がどこにあるか確認してください。そして実際に開いて、以下を確認:
- 防火管理者の氏名は現在の担当者か?
- 避難経路図は現在のレイアウトと合っているか?
- 従業員の役割分担は書かれているか?
アクション2:従業員に「火災が起きたらどうする?」と聞いてみる
朝礼や会議の場で、従業員に質問してみてください:
- 「火災報知器が鳴ったら、何をしますか?」
- 「避難後の集合場所はどこですか?」
- 「消火器の場所を知っていますか?」
答えられない人が多ければ、それが現状です。
アクション3:避難経路を実際に歩いてみる
図面だけでなく、実際に避難経路を歩いてください:
- 通路に障害物はないか?
- 非常扉は開くか?(鍵がかかっていないか?)
- 避難誘導灯は点灯しているか?
「図面上は正しい」でも、「実際には使えない」ケースは非常に多いのです。
なぜ専門家の支援が必要なのか?
「消防計画の見直し、自分たちでできないだろうか?」
そう思われる経営者様もいらっしゃるでしょう。



見直すだけならできます。
しかし、本当に実効性のある計画を作るには、専門的な知識と経験が不可欠です。
専門家だから分かること
- どこが法令違反になるか(見落としがちなポイント)
- 実際の火災でどこが危険になるか(現場経験からの視点)
- 消防署の立入検査で何を指摘されるか(消防署側の視点)
- 従業員が本当に動ける体制とは何か(訓練の実践的な設計)
書類を「作る」ことと、「使える計画を設計する」ことは、まったく別の技術なのです。
「うちの消防計画、大丈夫かな……?」
少しでも不安を感じたら、それが見直しのサインです。
最後に:書類ではなく、命を守る「道具」として
42年間の消防人生で、私は多くの火災現場を見てきました。
その中で、心の底から感じたことがあります。
「もし、きちんとした計画と訓練があれば、この被害は防げたかもしれない」
消防計画は、法律で義務付けられているから作るのではありません。
あなたの大切な従業員の命を守るために作るのです。
「作っただけ」の計画は、いざという時に何の役にも立ちません。
今日、この記事を読んでいただいたことをきっかけに、ぜひ一度、御社の消防計画を見直してみてください。
そして、少しでも不安を感じたら、私たちにご相談ください。
元消防局長として、そして行政書士として、御社の「本当の安全」を実現するお手伝いをいたします。
無料相談受付中・お気軽にご相談ください
安心はもちろん
防災の手間とコストを削減し、事業価値も高めます
消防法令への対応を適切に行うことは、リスク管理の一環として非常に重要です。しかし、複雑な手続きや現場での対応をすべて自力で行うのは困難です。
元消防士であり、消防法令に特化した当社だからこそ提供できるサポートにより、リスクを最小限に抑え、スムーズな事業運営を実現します。また消防設備にも精通しており、コスト削減のお手伝いもいたします。
今すぐ無料相談をご利用ください!
消防署対応や各種届出も安心してお任せいただけます。