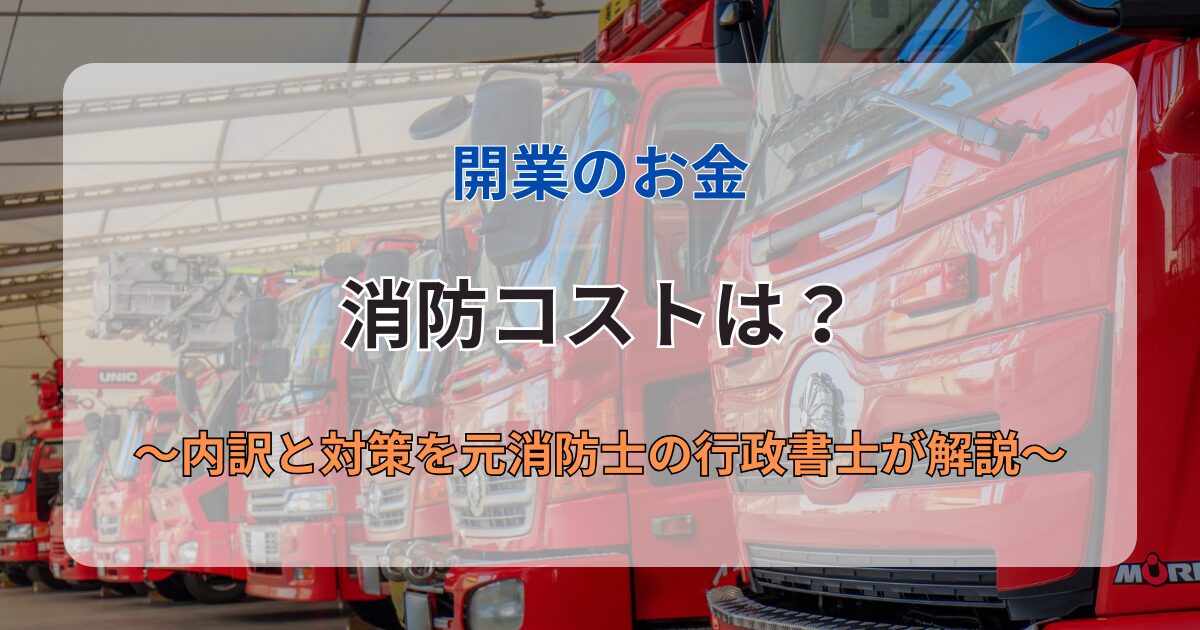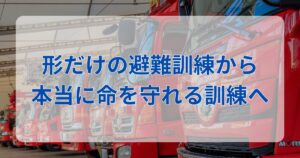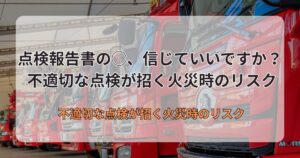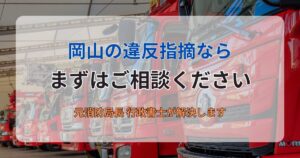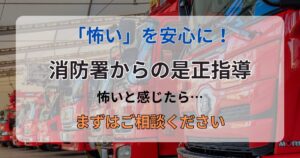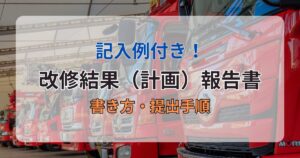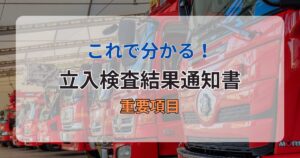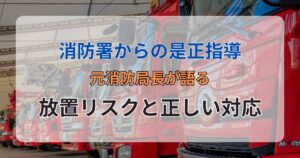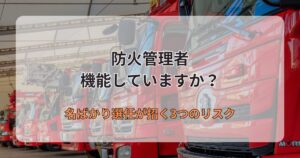新しい事業を始めるその一歩は、大きな希望と期待に満ちています。
店舗のコンセプト、内装デザイン、サービスの詳細、集客の方法など、考えを巡らせ、準備を進める時間は何物にも代えがたい貴重なものです。
しかし、開業までの道のりには、デザインやマーケティングといったワクワクする準備とは少し性質の異なる、「避けては通れない」重要なタスクも存在します。
その最たる例の一つが、消防法への適切な対応です。
「消防」と聞くと、「難しそう」「専門的でよく分からない」「結局いくらかかるのかが見えない」といった不安を感じ、つい後回しにしてしまったり、「うちのような小さな規模には関係ないだろう」と軽く考えてしまったりする方も少なくありません。
ですが、お客様やそこで働く従業員の安全、そして大切な事業資産を火災から守ることは、事業主として絶対に果たさなければならない責任です。
そして、安全確保のために定められた消防法は、あなたの新しいお店やオフィスにも等しく適用されます。
必要な消防用設備の設置や定期的なメンテナンス、消防署への各種届出といった義務を怠ると、開業自体が遅れたり、追加で想定外の費用が発生したり、最悪の場合、事業の継続が危ぶまれる事態に陥るリスクもゼロではありません。
このようなリスクを避け、安心して、そして円滑に事業をスタートさせるためには、開業前に消防関連で「何に、いくらくらいかかるのか」「どうすれば費用を抑えられるのか」といったお金の話をしっかりと把握しておくことが不可欠です。

本記事では、まさにこれから開業を迎えようとしているあなたが抱える、消防関連の費用に関する疑問や不安を解消するために、開業時にかかる消防関連コストの全体像、具体的な費用の内訳、そしてこれらのコストを賢く抑えるためのポイントを、分かりやすくお伝えします。
消防法への対応は複雑に感じるかもしれませんが、正しい知識を持ち、適切なステップを踏めば決して難しいものではありません。
この記事が、あなたの安全な事業スタートのための確かな一歩となり、無駄なコストを防ぎ、その後の安心経営へと繋がることを願っています。
なぜ開業時に消防関連コストが発生するのか? – 消防法の基礎知識
さて、開業にあたって「消防」への対応が必要であり、それに費用がかかる、とお伝えしましたが、そもそもなぜなのでしょうか?
その答えは、日本の法律である「消防法」にあります。
消防法が最も守りたいもの、それは「命」と「財産」
消防法は、火災を予防し、もし発生してしまった場合でも、その被害を最小限に抑えることを目的としています。そして、この法律が最も大切にしているのは、何よりも「人の命」です。次に、建物やそこにある大切な「財産」を火災から守ることも、消防法の重要な目的の一つです。
あなたがこれから開業するお店やオフィスには、お客様や従業員、そしてあなた自身が出入りし、様々な設備や商品といった財産が存在します。
万が一、そこで火災が発生すれば、これらの命や財産が一瞬にして危険に晒されてしまいます。
消防法は、そのような事態を防ぐために、あらかじめ建物の構造や設備、そしてそこで活動する人々に一定の基準や義務を課しているのです。
あなたの事業所も「防火対象物」です
消防法では、学校、病院、劇場、工場、そしてもちろん、店舗や事務所、飲食店なども含め、火災が発生した場合に被害が発生する可能性のある建物のことを「防火対象物」と定めています。
これからあなたが開業する事業所も、この「防火対象物」に該当します。
防火対象物の所有者や管理者は、その用途や規模に応じて、消防法で定められた基準に従わなければなりません。
事業者に課される主な「義務」
防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者など)には、消防法によって様々な義務が課せられます。開業時に特に関わってくる主な義務は以下の通りです。
- 消防用設備等の設置
万が一の火災に備え、消火器、火災報知設備、誘導灯といった消防用設備等を、法令の基準に従って設置すること。 - 消防用設備等の維持管理
設置した設備が、いざという時にきちんと機能するよう、定期的に点検し、整備すること。 - 消防計画の作成・届出
火災予防や火災発生時の初期対応、避難誘導などに関する計画(消防計画)を作成し、消防署に届け出ること(※一定規模以上の場合)。 - 防火管理者の選任
一定規模以上の防火対象物では、防火管理者を定め、消防計画に基づいた防火管理業務を行わせること。 - 消防訓練の実施
火災発生を想定した消火訓練や避難訓練を実施すること。
これらの義務を果たすためには、当然ながら費用が発生します。
例えば、義務付けられている設備が設置されていなければ購入・設置費用が、既存設備が基準を満たしていなければ改修費用がかかります。
また、設備は設置するだけでなく、定期的に点検・報告する義務があるため、その点検費用も継続的に発生します。
つまり、開業時に消防関連コストがかかるのは、単に手続きのためではなく、消防法という法律で定められた「安全を守るための義務」を果たすために必要な、正当な費用なのです。
まずはこの「なぜ必要か」という点を理解することが、その後の具体的な費用の内訳や対策をスムーズに把握する上で非常に重要となります。
開業時にかかる消防関連費用の具体的な内訳と相場感
前セクションで、消防法に基づく安全確保義務を果たすために消防関連コストが発生することをご理解いただけたかと思います。
では、具体的にどのような項目に、どれくらいの費用がかかる可能性があるのでしょうか。
ここでは、開業時に必要となる主な消防関連費用について、その内訳と一般的な相場感をご紹介します。
※ただし、これからご紹介する費用は、建物の用途や規模、構造、既存設備の有無、そして依頼する業者など、様々な要因によって大きく変動します。あくまで「目安」として参考にしてください。
消防用設備の設置費用
開業する事業所の用途や規模に応じて、法令で定められた消防用設備等を設置する必要があります。これらの設備の種類や数量によって、設置にかかる費用は大きく異なります。
多くの場合、これらの設置工事は専門の消防設備業者に依頼することになります。


消火器
火災の初期段階で、その炎を食い止めるために最も身近で重要な消火器具です。多くの事業所に設置義務があります。
役割
火災の初期段階で、その場にいる人が素早く火を消し止めること。
種類
粉末(ABC)消火器: 様々な火災に対応できるため広く普及しています。
強化液消火器、CO2消火器など、特定の火災に適したものもあります。
設置基準
建物の面積や用途に応じて、設置すべき場所や数が細かく定められています。
費用相場(目安)
本体価格: 1本あたり 5,000円~10,000円程度
設置費用: 本体を置くだけ、または壁掛けする程度であれば大きな工事は不要ですが、設置場所を示す標識の費用などが含まれる場合があります。
ポイント:適切な場所に、すぐに使える状態で設置されていることが重要です。
比較的安価な初期投資ですが、数が必要になるとそれなりの金額になります。


自動火災報知設備(自火報)
火災発生を早期に感知し、建物全体や関係者に警報で知らせることで、避難開始を促すための非常に重要な設備です。
役割
火災を自動で感知し、警報を発することで、建物内の人々に危険を知らせ、安全な避難を助けること。
主な構成要素
感知器: 設置場所の環境に応じて、熱、煙、炎などを感知するタイプがあります。
受信機: 各感知器からの信号を受信し、火災発生場所を表示・警報音を発します。
地区音響装置(ベル、スピーカーなど):建物内に火災を知らせる音響装置。
設置基準
建物の規模(延床面積、階数)や用途によって、設置が義務付けられるか、どのような種類の設備が必要かが決まります。
- 特に小規模な事業所向けには、設置基準が一部緩和された「特定小規模施設用自動火災報知設備」という区分があり、費用を抑えられる可能性があります。
費用相場(目安)
小規模店舗(100㎡未満程度、特定小規模含む): 20万円~50万円程度
一般的なテナント(数百㎡クラス): 50万円~200万円以上
大規模・複雑な建物: 数百万円~1,000万円以上
ポイント:
既存の建物に設置する場合、配線を隠すための工事が必要になり、内装費用と合わせて検討が必要です。
感知器の数や配線工事の規模が費用に大きく影響します。


誘導灯
火災や停電などの際に、避難口や避難経路を明らかにし、安全な場所へ誘導するための照明設備です。
役割
火災や停電時でも避難経路を示し、安全な避難をサポートすること。
種類
避難口誘導灯: 避難口の真上に設置され、「ここが逃げ口である」ことを示します。
通路誘導灯: 避難経路の壁などに設置され、避難方向を示します。
設置基準
建物の規模、構造、用途、通路の長さなどによって、必要な種類、大きさ、設置場所、数が細かく定められています。
費用相場(目安)
本体価格+設置工事費: 1台あたり 3万円~10万円程度
ポイント
消防法で定められた明るさや大きさを満たす必要があります。
非常用電源(バッテリー)が内蔵されており、定期的な点検が必要です。


スプリンクラー設備
火災の熱を感知して自動的に散水し、火災を初期段階で鎮圧することを目指す設備です。
役割
火災発生時、早期に自動で水を撒き、火を抑えること。
設置基準
比較的規模の大きな建物や、特定の用途(例えば、地下階や3階建て以上の一定規模の飲食店など)で設置が義務付けられることが多い、コストのかかる設備です。
費用相場(目安)
設備の規模、配管工事の複雑さ、水源の確保などによって大きく変動するため、数百万円~数千万円以上と高額になる傾向があります。
ポイント
設置義務があるかどうかは、建物の詳細な条件によります。
初期コストへの影響が非常に大きいため、物件選定の段階で設置義務の有無を確認することが極めて重要です。
その他の消防用設備
上記のほかにも、建物の条件によっては様々な消防設備が必要となる場合があります。
- 非常警報設備: 火災時に建物全体に警報(ベルや自動音声)を発する設備。
- 避難器具: 避難はしご、緩降機(ロープでゆっくり降りる器具)など。
- 屋内消火栓設備: 建物内に設置された消火栓。
- 連結送水管: 消防隊が外部から送水するための設備。
費用相場(その他設備): 設置規模や工事内容により大きく変動し、数十万円~数百万円以上になることもあります。
申請・届出にかかる費用
消防法に基づき、消防署への各種申請や届出が必要です。
これらの書類作成や手続きを自身で行うことも可能ですが、専門的な知識が必要な場合や、本業の準備で時間がない場合は、行政書士に代行を依頼することが多いです。
防火対象物使用開始届
概要
新たに事業を開始する際に、どのような用途で建物を使用するのかを消防署に知らせる届出です。
費用目安
自身で行う場合は費用はかかりません。
行政書士などに代行依頼する場合、3万円~5万円程度が一般的です。
消防用設備設置届出書
概要
新たに消防用設備等を設置した場合に、その内容を消防署に届け出る書類です。
設備の仕様や設置場所が分かる図面などが必要です。
費用目安
自身で行う場合は費用はかかりません。
代行依頼する場合、3万円~5万円程度が一般的です。
防火・防災管理者選任(解任)届
概要
一定規模以上の防火対象物で防火管理者(大規模な場合は防災管理者も)を選任・変更した場合に届け出る書類です。
費用目安
自身で行う場合は費用はかかりません。
代行依頼する場合、2万円~3万円程度が一般的です。
消防計画作成・提出
概要
防火管理者(または事業主)が作成する、火災予防や災害時の行動計画です。
作成後、消防署に提出が必要です。
費用目安
自身で作成する場合は費用はかかりません。
行政書士に依頼する場合、数万円程度かかることがあります。
その他の必要な申請・届出火気を使用する設備を設置する場合など、個別の状況に応じて追加の届出が必要になることがあります。
防火管理者関連費用
一定規模以上の防火対象物や特定の用途の事業所では、防火管理者を定める必要があります。
防火管理講習受講費用
概要
防火管理者となるためには、防火管理講習(甲種または乙種)を受講し修了する必要があります。
費用目安
講習の種類によって異なりますが、概ね1万円~2万円程度です。
防火管理業務委託費用(外部委託の場合)
概要
適切な人材がいない、本業に集中したい、といった理由から、防火管理業務を外部の専門業者に委託する場合があります。
費用相場
建物の規模や業務内容によって大きく変動しますが、年間数十万円以上かかることが一般的です。
設計・工事業者、専門家への依頼費用
消防用設備の設置工事や改修工事、あるいは複雑な申請手続きなどを専門家(消防設備士、工事業者、行政書士など)に依頼する場合の費用です。
これらの専門家への依頼費用が、上記の設備設置費用や申請・届出費用の多くを占めることになります。
消防設備の設置や改修は、消防法に基づいた専門的な知識と技術が必要です。
そのため、信頼できる業者選びが非常に重要になります。
安さだけで業者を選んでしまうと、手抜き工事や基準不適合となり、後々の手直しで余計な費用がかかったり、最悪の場合、消防検査に通らなかったりするリスクがあります。
東山行政書士事務所では、行政手続きだけでなく、お客様に代わって信頼できる消防設備会社をご紹介することも可能です。金額面だけでなく、確かな技術と実績を持つ業者選びのサポートもお任せください。
開業する事業所によって費用が大きく変わる要因
開業時にかかる可能性のある消防関連費用の様々な内訳と相場感を見てきました。
しかし、「では自分の場合は具体的にいくらかかるのだろう?」という疑問をお持ちだと思います。
同じような事業でも、消防関連の初期コストは大きく異なります。
その費用を左右する主な要因を理解しておくことが、正確な予算組みや、続くセクションで解説するコスト削減策を検討する上で非常に重要です。
特に消防設備に関しては、保険のように一度業者を決めると見直しをする事業者様は少なく、他より高い金額であっても気づいていないケースは多々あります。
事業所の用途・業種
開業する事業がどのようなサービスを提供するのか、つまり「用途」が消防法上の基準に最も大きく影響します。
火災リスクの高い用途
飲食店(特に火を使う場合)、物品販売店(不特定多数が出入りし、商品が燃えやすい場合がある)などは、事務所などに比べて火災リスクが高いとみなされ、より厳格な消防設備基準が適用される傾向があります。
避難の難易度
病院や高齢者施設のように、自力での避難が難しい人が利用する施設は、避難誘導や設備の基準が厳しくなります。
不特定多数の出入り
映画館や劇場、百貨店、多数の人が集まる飲食店などは、避難誘導計画や設備の基準が厳しくなります。



例えば、同じ面積のテナントでも、事務所として使用する場合と、同じ面積で飲食店として使用する場合では、必要となる火災報知設備の感知器の種類や数、誘導灯の設置基準、さらにはスプリンクラー設備の設置義務の有無などが異なり、結果として消防設備費用に大きな差が生じます。
建物の構造・規模・収容人数
開業する事業所が入居する「建物そのもの」の条件も、費用に大きく影響します。
延床面積
建物の延床面積が広くなるほど、必要となる消防設備の数や種類が増える傾向があります(例:一定面積以上でスプリンクラー義務化)。
階数
建物の階数が高くなるほど、避難設備の基準が厳しくなったり、連結送水管などが必要になったりします。地下階や無窓階(窓のない階)も避難が難しいため、基準が厳しくなることが多いです。
建物の構造
耐火構造の建物は火災が燃え広がりにくいため、一部の設備基準が緩和されることがあります。木造など燃えやすい構造の場合は、より厳格な基準が適用される可能性があります。
収容人数
事業所に同時に滞在する可能性のある人数が多いほど、避難設備や誘導計画に関する基準が厳しくなります。
物件の状態(居抜き vs 内装がない物件、築年数、改修の有無)
開業する場所がどのような状態かも、初期コストに大きく影響します。
内装がない物件
内装も設備も何もない状態からのスタートです。この場合、消防設備もゼロから設計・設置する必要があるため、費用は高額になる傾向があります。
居抜き物件
以前のテナントが使用していた内装や設備が残っている状態です。消防設備もそのまま残っている場合がありますが、その設備があなたの新しい事業の用途や規模に適合しているか、また現行の消防法基準を満たしているかを確認することが不可欠です。
適合していれば新規設置費用を抑えられますが、基準を満たしていない場合は改修や交換が必要となり、かえって費用がかさむケースもあります。
築年数・改修の有無
建物の築年数が古い場合や、過去に大規模な改修が行われているかによって、既存の消防設備が現在の基準に適合しているかどうかが変わってきます。
大規模な改修を行う場合は、それに合わせて消防設備の改修も必要になることがあります。
管轄消防署の判断や指導
同じ消防法でも、解釈や運用について、各地域の消防署によって若干の指導方針の違いが見られることがあります。また、個別の物件の構造や状況に応じて、消防署から追加の指導が入る可能性もあります。
※開業前に管轄の消防署や専門家(消防設備士、行政書士など)に相談し、必要な設備や手続きについて事前に確認しておくことが、予期せぬ費用増加を防ぐ上で非常に有効です。
依頼する業者や設備のグレード
どの消防設備業者や専門家に依頼するかによっても費用は変動します。
業者による見積もりの差
同じ工事内容でも、業者によって見積もり額に差が出ることはよくあります。
複数の業者から相見積もりを取ることが重要です。
設備のグレード
消防設備には様々なメーカーやグレードがあり、選ぶ製品によって費用が変わる場合があります。
ただし、法令で定められた基準を満たすことが大前提です。
これらの要因が複合的に組み合わさることで、開業時の消防関連コストは大きく変動します。
あなたの開業ケースでは、これらの要因がどのように関わってくるのかを把握することが、正確な費用予測の第一歩となります。
開業時の消防関連コストを賢く抑えるためのポイント
開業資金は限られていることが多く、可能な限りコストを抑えたいと考えるのは当然です。消防関連費用も例外ではありません。しかし、最も重要なのは、安全確保と消防法への適合性を決して損なわないことです。
ここでは、安全と法律を守りながら、開業時の消防関連コストを賢く抑えるためのポイントをご紹介します。
物件契約前に消防設備の状況を徹底的に確認する
開業コストを抑える上で、最も早期かつ効果的な対策の一つです。
なぜ重要か
物件契約後に消防設備に問題が見つかると、契約解除が難しかったり、改修費用が想定外の大きな負担になったりするリスクがあります。
事前に把握できれば、その費用を見込んだ上で交渉したり、他の物件を検討したりといった対応が可能です。
確認するポイント
- どのような消防設備(消火器、報知設備、誘導灯など)が既存で設置されているか。
- それが現在の消防法、特にあなたの開業する事業の用途や規模に適合しているか。
- 設備の設置年や点検状況(報告書の有無など)。
古すぎる、または点検されていない設備は改修や交換が必要になる可能性が高いです。
誰に確認するか
不動産業者、建物の所有者や管理会社に問い合わせるのが基本です。可能であれば、消防設備の専門家(消防設備士など)や行政書士に内見に同行してもらい、専門的な視点から既存設備をチェックしてもらうのが最も確実です。
居抜き物件の既存消防設備を可能な限り有効活用する
居抜き物件の最大のメリットは、内装だけでなく既存の設備を活用できる可能性がある点です。消防設備も例外ではありません。
メリット
既存の設備が新しい事業の基準に適合していれば、新規設置にかかる費用を大幅に削減できます。
注意点
- 前のテナントの用途とあなたの用途が異なる場合、必要な設備基準が違う可能性があります。
- 既存設備が現行の消防法に適合しているか、劣化していないかを必ず確認する必要があります。素人判断は禁物です。
- 既存設備を改修して使用する場合でも、改修工事やそれに伴う申請費用は発生します。
物件契約前に、既存設備が活用可能か、どの程度の改修が必要かを専門家(消防設備業者や行政書士)に診断してもらうことが不可欠です。
診断費用はかかりますが、後々の手戻りや高額な改修費用を防ぐための「賢い先行投資」と考えましょう。
複数の消防設備業者から必ず相見積もりを取る
消防設備の設置や改修工事、点検費用は、業者によって見積もり額に差が出ることがあります。適正な価格で依頼するためには、複数の業者から見積もりを取って比較検討することが基本です。
比較するポイント
合計金額
当然ながら重要ですが、安すぎる業者には注意が必要です。
内訳の明確さ
どのような工事にいくらかかるのか、詳細が明確か確認します。一式計上になっている場合は詳細を求めましょう。
工事内容の妥当性
提案された工事内容が、消防法上本当に必要な範囲か、過剰な提案ではないか(専門家でないと判断が難しい場合があります)。
実績と信頼性
その分野での実績が豊富か、口コミや評判は良いか、担当者の対応は丁寧かなども判断材料になります。
注意点
価格だけで業者を選ばず、工事の質や信頼性も必ず確認しましょう。手抜き工事は安全に関わるだけでなく、結局やり直しで費用がかさむ最大の原因となります。
自治体の補助金・助成金制度を活用できないか情報収集する
国や地方自治体によっては、中小企業の開業支援や、防災・防火対策に関する補助金や助成金制度を設けている場合があります。
情報収集の方法
開業する市町村や都道府県の公式ウェブサイトで「開業」「創業」「補助金」「助成金」「防災」「防火」といったキーワードで検索する。
地元の商工会議所や中小企業支援センターに問い合わせてみる。
ポイント
- 多くの場合、申請期間や条件が決まっています。早めに情報を収集し、対象となるか確認することが重要です。
- 補助金や助成金は、申請すれば必ず受けられるものではありません。また、多くの場合は後払い(立替払い)となります。
小規模施設に関する消防法上の特例などを検討・活用する
建物の規模や用途によっては、消防法上の設備基準が一部緩和される「特例」が適用される場合があります。
比較的小規模な飲食店などでは、一般的な自動火災報知設備よりも安価な「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置で済む場合があります。
開業する事業所の詳細な条件(用途、面積、階数など)を管轄の消防署や消防設備の専門家に伝え、適用可能な特例がないか確認してもらいましょう。
自身で対応可能な手続き(消防計画作成など)は挑戦してみる
消防署への申請・届出や消防計画の作成など、一部の手続きは専門家に依頼せずご自身で行うことも可能です。
メリット
専門家への代行費用を削減できます。
挑戦しやすい手続き
- 防火・防災管理者選任(解任)届の提出(管理者を選任した場合)
- 消防訓練実施計画書の提出(訓練前に)
- 消防計画の作成(テンプレートなどを活用)
注意点
消防法は専門的であり、書類に不備があると受理してもらえなかったり、手続きに時間がかかったりする可能性があります。消防署の窓口で相談しながら進めるか、自信がない場合は一部だけでも専門家に依頼することも検討しましょう。
信頼できる専門家(行政書士、消防設備士等)に早い段階で相談する
費用を抑えるための最大のポイントは、「無駄な費用」をかけないこと、そして「手戻り」を防ぐことです。
そのためには、消防法に詳しい専門家に早い段階で相談することが非常に有効です。
相談するメリット
- あなたの事業所に本当に必要な消防設備や手続きを正確に教えてもらえる。
- 物件契約前に、消防法上の問題を洗い出してもらえる。
- 消防署との難しい協議を代行・サポートしてもらえる。
- 信頼できる消防設備業者を紹介してもらえる。



事前に正確な情報を得ることで、不要な設備を設置したり、基準を満たさない工事をしてやり直しになったりといった、無駄な出費や手戻りを未然に防ぐことができます。
専門家への相談費用はかかりますが、トータルで見ればコスト削減に繋がる可能性が高いです。
当事務所は次は自分でもできるように、分かりやすく説明もいたします。
開業までの消防関連手続きの流れと注意点
開業の準備は多岐にわたりますが、消防関連の手続きもその中に組み込んで計画的に進める必要があります。これらの手続きを円滑に進められるかどうかが、予定通りの開業ができるかどうかに直結します。
開業までの大まかな消防関連手続きの流れと、各段階での重要な注意点を見ていきましょう。
ステップ1:物件選定と契約前の事前確認
最も最初にして、最も重要なステップです。ここで問題を把握できるかどうかで、後々の手間やコストが大きく変わります。
- 検討している物件が、開業したい事業の用途で使用可能か(建築基準法や都市計画法も関連しますが、消防法上の問題がないかも確認)。
- 物件に既存の消防設備が設置されているか、その種類や設置年などを確認。
- 建物の構造(面積、階数、耐火構造など)を確認。
注意点
- 不動産業者や物件オーナーに任せきりにせず、必ずあなたの開業する事業の用途を伝え、必要な消防設備や法的な問題がないか具体的に確認してもらいましょう。
- 可能であれば、契約前に管轄の消防署に物件情報を伝え、必要な消防設備や改修点について事前相談を行うことを強くお勧めします。
- 消防設備士や行政書士といった専門家に相談・同行を依頼し、専門的な視点から設備の適合性や改修の必要性を診断してもらうのが最も確実です。
この段階で必要な改修費用などが判明すれば、契約条件に反映させたり、他の物件と比較検討したりできます。契約後に基準不適合が判明すると、大幅な追加費用や工期遅延に繋がりかねません。
ステップ2:設計・内装工事と消防設備の設置工事
物件が決まったら、内装工事と並行して必要な消防設備の設計と設置工事を進めます。
- 内装設計と合わせて、消防法に基づいた消防設備の設計を行います。
- 必要な消防設備の設置または改修工事を、消防設備業者に依頼して実施します。
- 厨房の設置など、火気を使用する設備を設ける場合は、火気使用設備等設置届などの提出が必要になることがあります。
注意点
- 内装業者と消防設備業者の連携が非常に重要です。配線のルート確保など、工事の順番や内容について密に情報共有を行いましょう。
- 消防設備の設計や工事は専門性が高いため、必ず消防設備士の資格を持つ信頼できる業者に依頼してください。手抜き工事や基準不適合は、後の消防検査で必ず発覚し、やり直しとなります。
- 工事の途中で消防法に関わる変更が生じる場合は、必ず事前に消防署に相談し、指導を受けてください。



東山行政書士事務所では、信頼できる消防設備会社の紹介も致しております。業者選びで失敗したくない人は当事務所にご相談ください。
ステップ3:消防署への各種届出・申請
必要な設備の設置工事が完了したら、開業前に消防署へ各種届出や申請を行います。
- 最も重要なのが「防火対象物使用開始届」の提出です。事業を開始する前に必ず提出が必要です。建物の概要、用途、構造などが分かる書類や図面を添付します。
- 新たに消防用設備を設置・変更した場合は、「消防用設備設置届出書」を提出します。設備の詳細な仕様や設置場所を示す書類、試験結果報告書などを添付します。
- 防火管理者を選任した場合は、「防火管理者選任(解任)届」を提出します。
- その他、個別の状況に応じて必要な届出を行います。
注意点
- これらの届出は、提出期限が定められているものがあります。
(例:使用開始届は使用開始の概ね7日前まで)
期日を過ぎると手続きに影響が出る可能性があります。 - 提出書類には専門的な図面や書類が必要となる場合があり、不備があると受理してもらえません。
- 書類作成や手続きに不安がある、または本業に集中したい場合は、行政書士などの専門家に代行を依頼することを検討しましょう。
ステップ4:消防検査の実施
届出が完了すると、消防署の担当者による「消防検査(立入検査)」が実施されます。
これは、設置された消防設備が法令に適合しているか、避難経路が確保されているかなどを実際に確認する重要なステップです。
- 消防署の担当者が実際に事業所を訪れ、設置されている消防設備(消火器の位置、火災報知設備の感知器やベルの設置状況、誘導灯の点灯、避難器具の設置状況など)を一つ一つ確認します。
- 避難経路に物が置かれていないか、防火扉が閉まるかなどもチェックされます。
- 防火管理者や消防計画、消防訓練の準備状況についても確認されることがあります。
注意点
- 消防検査で指摘を受けた箇所は、改善が完了するまで開業できません。
- 検査当日に設備の不備や書類の不備が発覚すると、後日改めて改善内容を報告したり、再検査を受けたりする必要が生じ、開業が遅れる最大の原因となります。
検査に立ち会う際は、設置した消防設備について説明できるよう、事前に業者と内容を確認しておきましょう。
行政書士に立ち会いを依頼することも可能です。
ステップ5:検査合格と開業
消防検査で指摘箇所がなく、法令に適合していると認められれば、検査は合格となります。
消防署から「防火対象物使用開始届出済証」などが交付されます。
これが、消防法上の手続きが完了し、事業を開始できることの証明となります。
※検査に合格した後も、安全な事業運営のためには継続的な防火管理が重要です。
手続き全体の注意点とスケジュール遅延リスク
開業までの消防関連手続きは、上記のステップを計画的に進める必要があります。
特に注意すべきは、消防検査で不備が発覚することによるスケジュール遅延リスクです。
- 早い段階での情報収集と事前相談
物件契約前から専門家や消防署に相談する。 - 信頼できる専門家・業者の選定
知識と技術のあるプロに設計・工事・手続きを依頼する。 - 関係者間の密な連携
内装業者、消防設備業者、行政書士などがしっかり連携して情報共有する。 - 余裕を持ったスケジュール設定
消防検査での指摘事項改善や再検査の可能性も考慮し、ぎりぎりのスケジュールにならないようにする。
消防関連の手続きは煩雑で専門的な知識も必要ですが、安全な開業のためには避けて通れません。
ご自身での対応が難しい部分や、不安な点は、遠慮なく専門家を頼ることを検討しましょう。
開業後も継続して発生する消防関連費用と義務
無事に消防検査に合格し、待ちに待った開業を迎えた後も、消防法に関する義務がなくなるわけではありません。
むしろ、開業後は事業を継続していく上で必要な、継続的な消防関連の費用と義務が発生します。
これらのランニングコストと義務をあらかじめ把握しておくことは、長期的な事業計画を立てる上で非常に重要です。



業者にまかせて何も知らないと言う事業様も少なくありません。
コストとして大きくないと考えているのかもしれませんが、見直しすることで大幅にコスト削減できる場合もあります。
消防用設備等の定期点検
開業時に設置した消防用設備等は、いざという時に確実に機能するよう、定期的な点検と消防署への報告が義務付けられています。
点検の種類と頻度
点検には、機器点検と総合点検の2種類があります。
- 機器点検
- 内容
消防用設備等の外観や簡単な操作で、損傷がないか、正常に機能するかを確認します。 - 頻度
6ヶ月に1回以上 行う必要があります。
- 内容
- 総合点検
- 内容
消防用設備等を実際に作動させたり、機能を確認したりする、総合的な点検です。 - 頻度
1年に1回以上 行う必要があります(設備の種類によっては異なる場合があります)。
- 内容
これらの点検は、消防設備士または消防設備点検資格者という専門の資格を持つ人が行う必要があります。
事業所の関係者(防火管理者など)が簡易な機器点検の一部を行うことも認められる場合がありますが、専門的な知識と技術が求められるため、多くの場合は外部の専門業者に委託します。
点検費用と報告義務
点検にかかる費用は、設置されている消防設備の種類や数、建物の規模などによって大きく異なります。
- 点検費用相場(目安):
- 比較的小規模な事業所(消火器、自火報、誘導灯など基本設備のみ): 年間数万円~10万円程度
- 大規模な事業所や設備が多い場合: 年間数十万円~数百万円以上
- 報告義務: 点検結果は、消防長または消防署長に報告する義務があります。
- 特定防火対象物(百貨店、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物):1年に1回 報告が必要です。
- その他の防火対象物(事務所、共同住宅など):3年に1回 報告が必要です。
点検を怠ったり、虚偽の報告をしたりすると、法律違反となり罰則の対象となる可能性があります。また、何より、いざという時に設備が作動せず、人命に関わる重大な事故に繋がりかねません。
防火対象物定期点検・防災管理点検(必要な場合)
建物の用途や規模によっては、消防設備点検とは別に、建物全体の防火・防災管理状況について、定期的な点検と報告が義務付けられています。
- 対象: 比較的大規模な建物や、特定の用途(多数の人が利用する建物など)
- 内容: 建物全体の防火・防災管理体制、避難経路、防火戸の管理状況など、設備以外の管理状況も点検します。
- 頻度: 1年に1回 点検を行い、その結果を消防署に報告する必要があります。
- 点検者: 防火対象物点検資格者、または防災管理点検資格者という専門資格を持つ人が行います。
- 費用相場(目安): 建物の規模によりますが、年間数万円~数十万円程度かかることが多いです。
防火管理者の責務と関連費用
一定規模以上の事業所で選任した防火管理者は、防火管理業務を継続的に行う義務があります。
- 主な責務:
- 消防計画に基づいた防火管理業務の実施。
- 消防用設備等の維持管理に関する助言・監督。
- 消防訓練の実施。
- 従業員への防火・防災教育。
- 消防署への報告・連絡。
- 関連費用:
- 社内の従業員が兼任する場合は、直接的な追加費用は発生しませんが、その従業員の人件費や、講習参加にかかる費用が発生します。
- 外部の専門業者に防火管理業務を委託している場合は、委託費用が継続的に発生します。
消防訓練の実施
火災発生時に従業員が適切に行動できるよう、定期的な消防訓練(消火訓練、避難訓練など)の実施も義務付けられています。
- 頻度:
- 一般的には1年に2回以上の実施が推奨されています。
- 特定の防火対象物(例: 病院、学校、ホテルなど)では、より頻繁な実施が義務付けられている場合があります。
- 費用:
- 自社で行う場合は、消火器の訓練用水の費用や、資料作成の手間などがかかります。
- 消防署に相談すれば、訓練方法のアドバイスや、立ち会い、資材の貸し出しを受けられる場合があります(無料または実費)。
- 外部の専門業者に訓練の企画・実施協力を依頼する場合は、費用が発生します。
その他の継続的な費用
上記以外にも、必要に応じて以下の費用が発生する可能性があります。
- 消防用設備等の修繕・交換費用: 点検の結果、設備の不具合が見つかった場合や、設備の耐用年数が来た場合の修繕や交換にかかる費用です。
- 消耗品費用: 消火器の薬剤詰め替え(使用期限がある)、誘導灯のバッテリー交換などにかかる費用です。
開業後のこれらの継続的な費用や義務も、安全な事業運営のためには欠かせないものです。計画的に予算を確保し、適切に実施していくことが重要です。
ご自身での管理が難しい場合は、これらの業務を外部に委託することも可能です。
まとめ:安全な開業と継続的な安心のために、専門家のサポートを



この記事では、開業時にかかる消防関連コストに焦点を当て、「なぜ費用が必要なのか」という基本的な理由から、具体的な費用の内訳、費用を左右する要因、そしてコストを賢く抑えるためのポイント、さらには開業までの手続きの流れや開業後の継続的な義務と費用について、解説してきました。
この記事では、開業時にかかる消防関連コストに焦点を当て、「なぜ費用が必要なのか」という基本的な理由から、具体的な費用の内訳、費用を左右する要因、そしてコストを賢く抑えるためのポイント、さらには開業までの手続きの流れや開業後の継続的な義務と費用について、網羅的に解説してきました。
改めて振り返ると、開業時の消防関連コストは、主に以下の要素から成り立っています。
- 消防用設備の設置費用
消火器、火災報知設備、誘導灯など、法令で定められた設備を設置するための費用。建物の用途や規模によって大きく変動します。 - 申請・届出費用
消防署への各種書類作成や提出にかかる費用。自身で行うか、専門家に依頼するかで変わります。 - 防火管理者関連費用
防火管理者の選任や講習、外部委託にかかる費用(対象となる場合)。 - 設計・工事業者、専門家への依頼費用
消防設備の設計、工事、行政手続き代行などを依頼する専門家への費用。
これらの費用は、物件の状態(居抜き物件か新規物件か)や事業の用途、建物の規模など、様々な要因によって大きく変動することを解説しました。
そして、これらのコストを抑えるためには、物件契約前の確認、居抜き設備の有効活用、複数の業者からの相見積もり、補助金の活用、そして何よりも早い段階での専門家への相談が重要であるというポイントをお伝えしました。
開業までの手続きは、物件確認から始まり、設備の設置工事、各種届出、そして消防検査を経て、ようやく開業に至ります。この過程で不備があると、スケジュールの遅延や追加費用の発生に繋がるため、計画的に進めることが不可欠です。
また、開業後も消防用設備の定期点検や、防火管理者の責務、消防訓練の実施といった継続的な義務と、それに伴う費用が発生し続けることもご理解いただけたかと思います。
安全確保と法令遵守が大前提
消防関連コストを検討する上で、最も忘れてはならないのが、その根底にある「人命と財産を守る」という目的、そして「消防法を遵守する」という事業主の義務です。
費用を抑えることは重要ですが、それが安全性の低下や法令違反に繋がっては本末転倒です。
適正なコストをかけ、必要な対応をしっかりと行うことが、結果としてお客様からの信頼獲得や、安心して事業を継続していくための基盤となります。



災害なんて自分には関係ないと思われているかもしれません。
しかし、私は消防士として数えきれない火災現場に出動し、大規模災害での活動経験から、決して他人事ではないと言えます。
もしもに備えることは、事業継続のためにも非常に重要なことです。
消防関連の悩みは、専門家にご相談ください
開業準備は、本業の立ち上げに加えて、様々な手続きや専門知識が必要となる場面が多くあります。
- 消防関連の手続きが複雑そうで、どこから手を付ければ良いか分からない
- 自分の物件に必要な設備や正確な費用を知りたい
- 信頼できる消防設備業者を紹介してほしい
- 本業の準備に集中したいので、消防関連の手続きは専門家に任せたい
このように感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
消防法への対応は専門性が高く、慣れない作業に多くの時間と労力を費やしてしまう可能性があります。
また、誤った判断や手続きの不備は、後々のトラブルや余計な費用に繋がるリスクも伴います。
東山行政書士事務所では、あなたの開業を消防関連の側面からもしっかりとサポートいたします。
私たちは、開業に必要な各種行政手続きの代行はもちろん、
- お客様の事業内容や物件に合わせた、必要な消防設備や手続きに関する正確な情報の提供
- 信頼できる消防設備会社のご紹介
- 消防署との事前相談や検査対応のアドバイス
- 防火管理者選任や消防計画作成に関するサポート
など、消防関連の「分からない」や「困った」を解決し、お客様が安心して開業準備を進められるよう、きめ細やかなサポートを提供しております。
複雑な消防関連の手続きや専門業者とのやり取りは、ぜひ私たちにお任せください。お客様が本業のスタートに全力を注げるよう、専門家としてしっかりと伴走いたします。
開業時の消防関連コストや手続きにご不安がある方、信頼できる専門家のサポートを受けたい方は、ぜひ一度、東山行政書士事務所にご相談ください。
無料相談受付中・お気軽にご相談ください
安心はもちろん
防災の手間とコストを削減し、事業価値も高めます
消防法令への対応を適切に行うことは、リスク管理の一環として非常に重要です。しかし、複雑な手続きや現場での対応をすべて自力で行うのは困難です。
元消防士であり、消防法令に特化した当社だからこそ提供できるサポートにより、リスクを最小限に抑え、スムーズな事業運営を実現します。また消防設備にも精通しており、コスト削減のお手伝いもいたします。
今すぐ無料相談をご利用ください!
消防署対応や各種届出も安心してお任せいただけます。